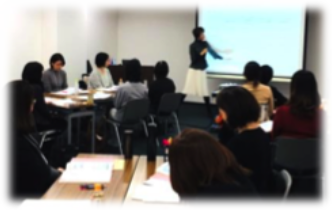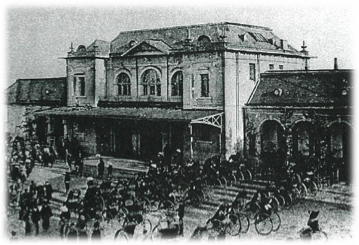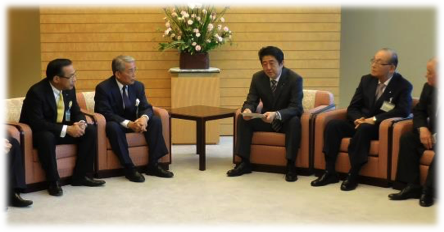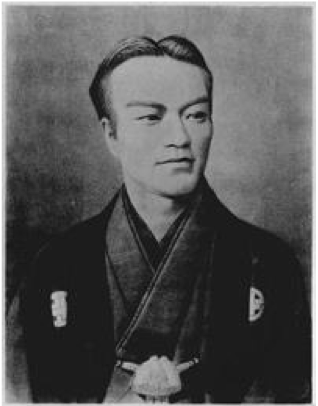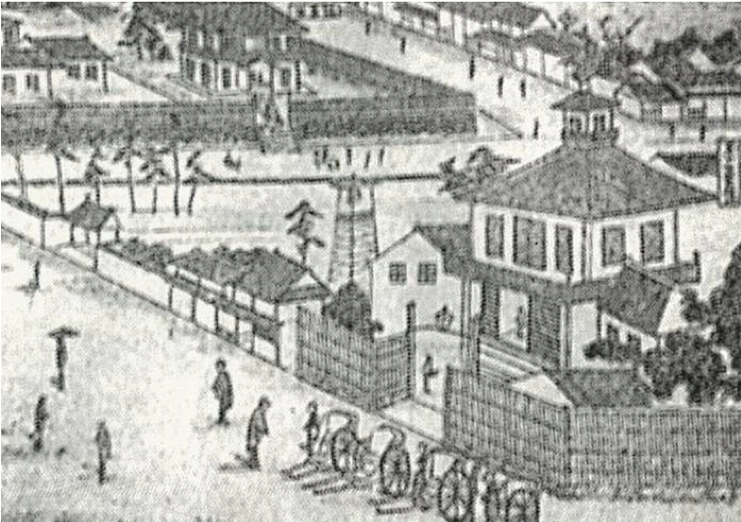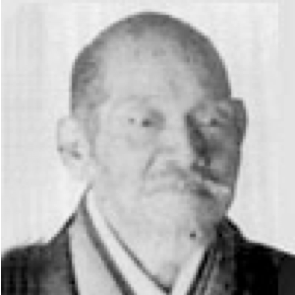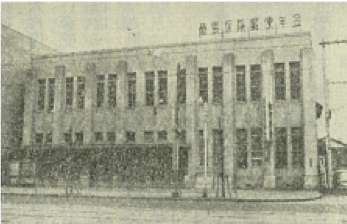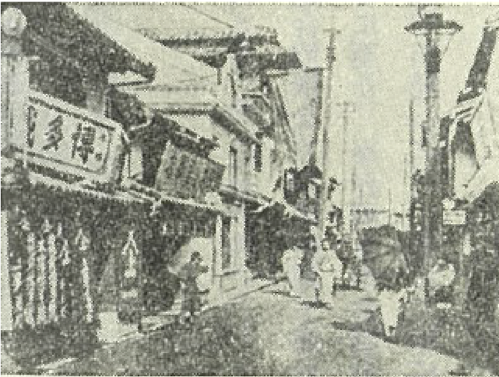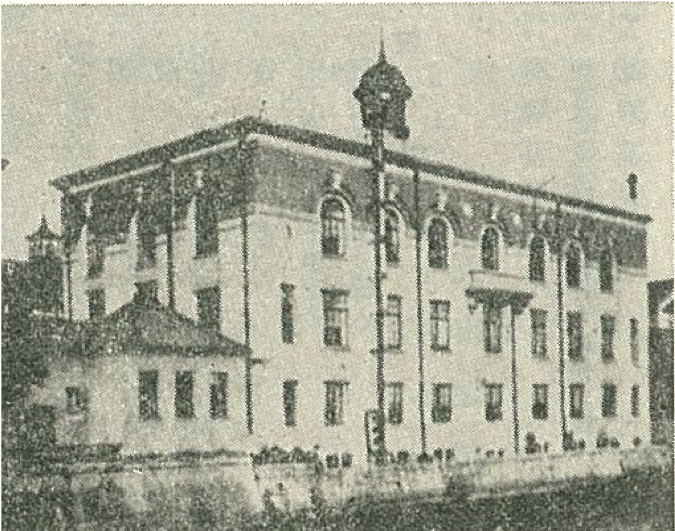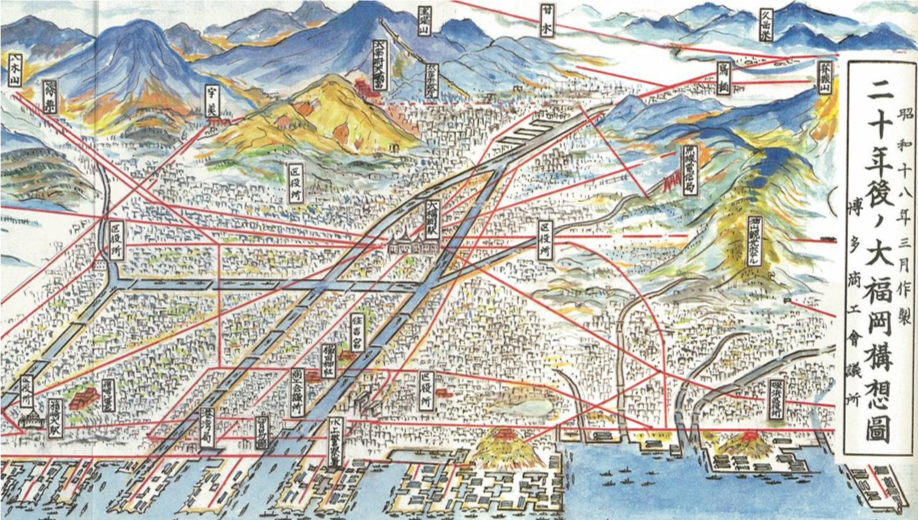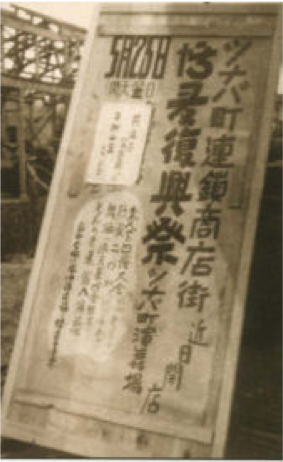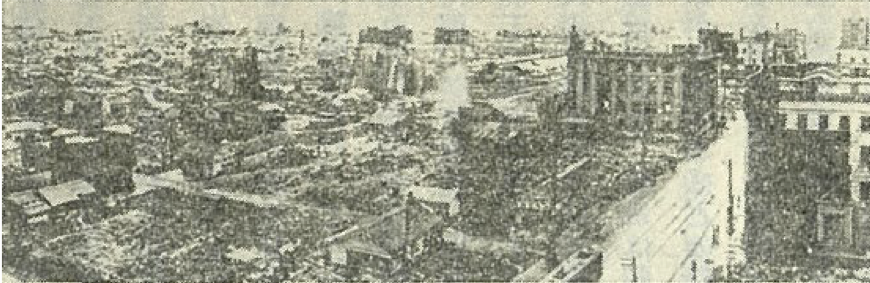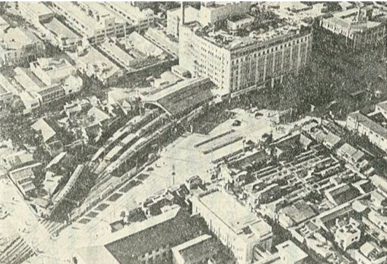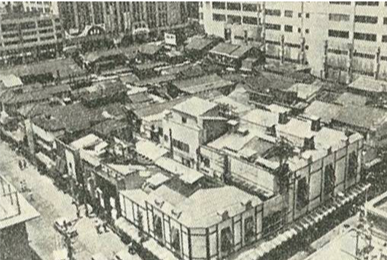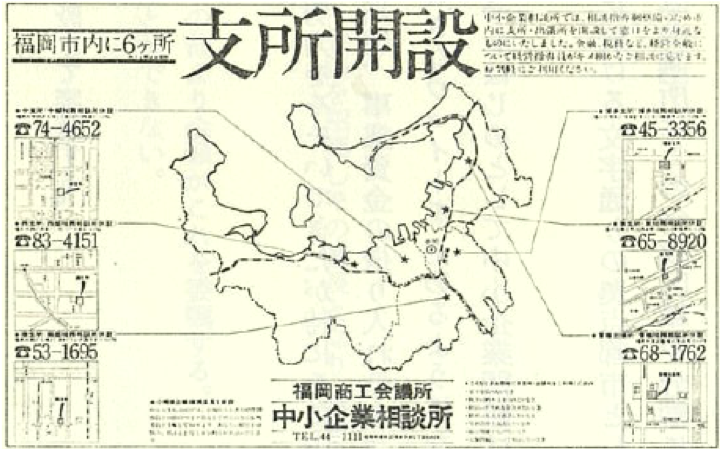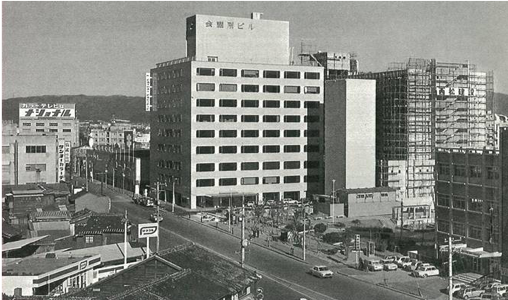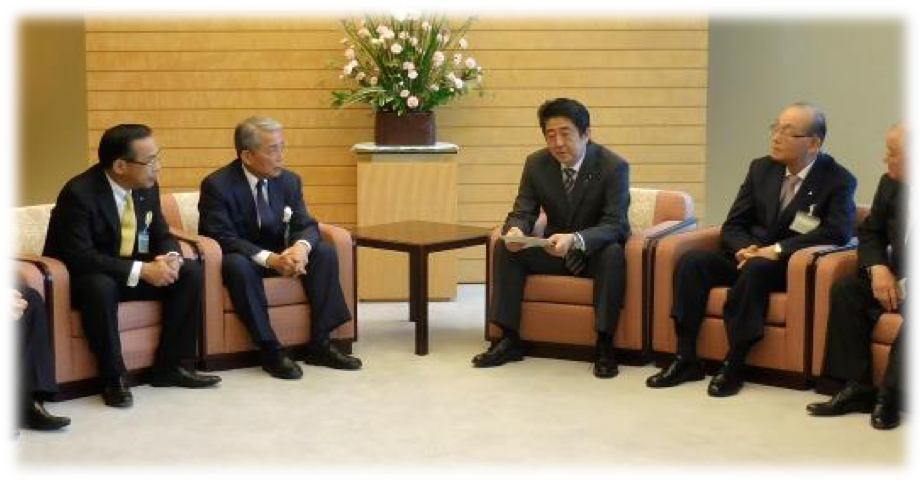福岡商工会議所の軌跡

福岡商工会議所の軌跡
- History -


1891明治24年
農商務大臣を主務大臣とする商法会議所条例のもと、
「博多商業会議所」設立


1897明治30年
東中洲に発電所を設置

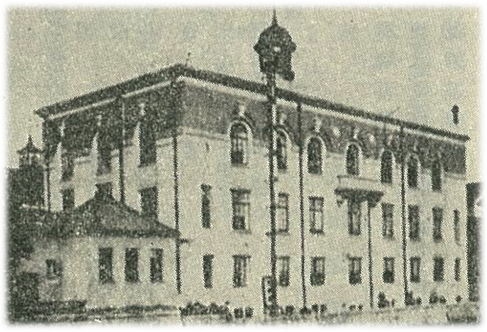
ひときわ立派だった。
昭和45年までの47年の歳月にわたり、商工業者の苦楽が刻み込まれた。
1924大正13年
東中洲の大火から博多商業会議所所屋を再建
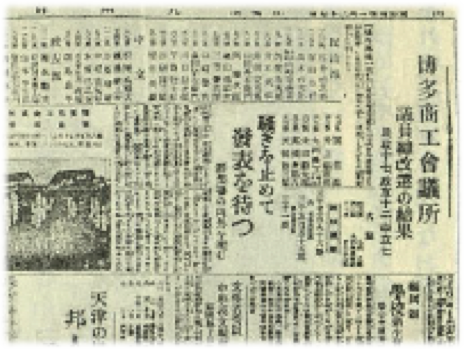
1928昭和3年
新法に基づく博多商工会議所の発足
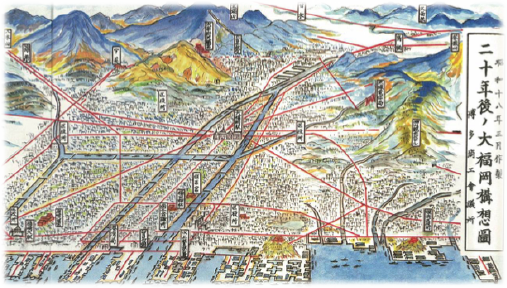

この廃墟の中から福岡市民は立ちあがった
1946昭和21年
社団法人福岡商工会議所が設立

戦後の焼け野原から復活

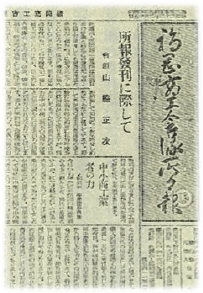
1950昭和25年
中小企業相談所を開所
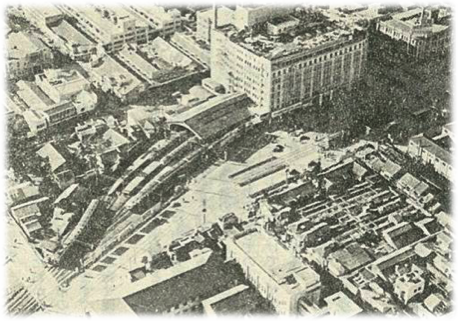
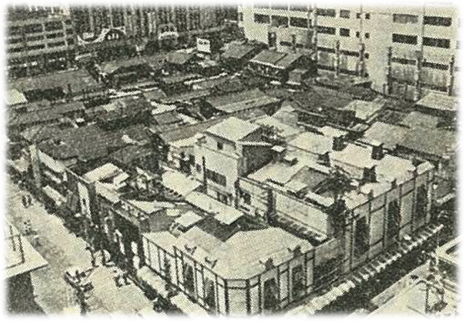
1968昭和43年
高度成長と街づくりに貢献
商店街再開発事業に対する固定資産税の大幅削減要望

1970昭和45年
福岡商工会議所ビル建設
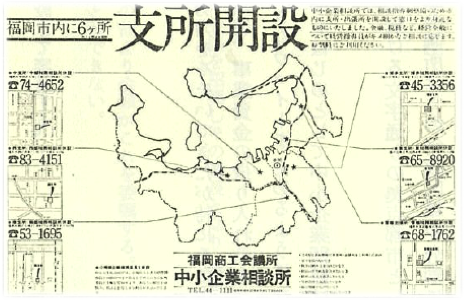

1982昭和57年
第1回博多うまかもん市を開催

1985昭和60年
第1回ふくおか経済人余技展を開催

平成5年、県庁と福岡空港将来構想検討委員会設立

よかトピアどんたくを開催

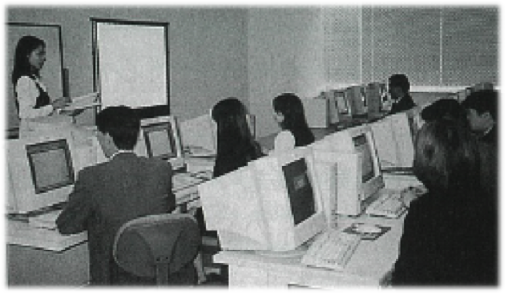
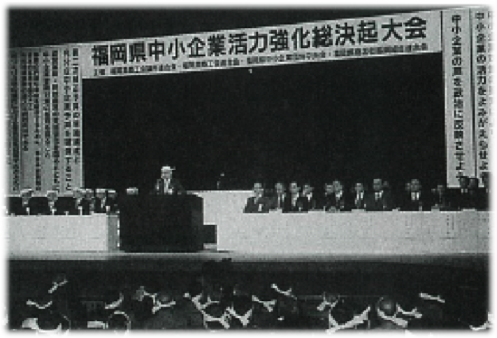
1999平成11年
福商パソコンスクールを開講
福岡県中小企業活力強化総決起大会

2000平成12年
新人芸妓の育成を開始

2001平成13年
九州ビジネスショウで福商ITフェアを開催

2004平成16年
福商ビジネス倶楽部設立


2014平成26年
Food EXPO Kyushuを開催

2015平成27年
ラグビーワールドカップ試合招致を実現
新たな経済・社会を生き残る、地域・中小企業を創造する
アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築



地域を支え、成長し続ける商工業者の支援